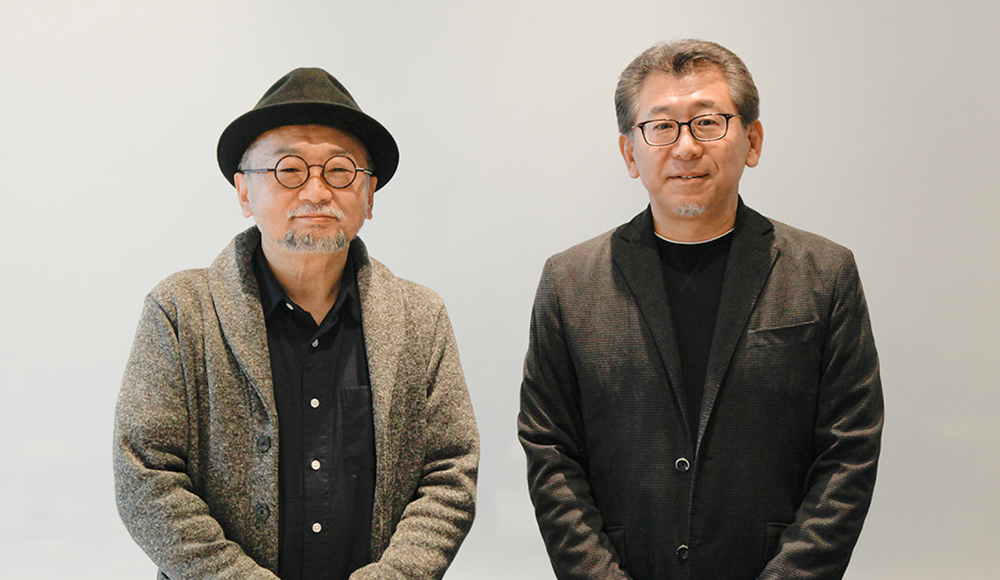
コロナ禍で社会変革の加速化が指摘される昨今。仕事の方法から雇用形態、評価指針やチームビルディングなど、これからのトレンドとして予測される"さまざまな変化"について、谷崎テトラさん、林展宏さんを迎え座談会を実施し、お話を伺いました。その様子を全3回の連載でお届けします。

1964年、静岡生まれ。環境・平和・アートをテーマにしたメディアの企画構成・プロデュースを行う。価値観の転換(パラダイムシフト)や、持続可能社会の実現(ワールドシフト)の発信者&アーティストとして活動は多岐に渡る。アースデイ東京などの環境保護アクションの立ち上げや、国連 地球サミット(RIO+20)など国際会議のNGO参加、SDGs、ピースデー(国際平和デー)などへの社会提言・メディア発信に関わるなど、持続可能な社会システムに関して深い知見と実践の経験を持つ。世界のエココミュニティを取材し、エコビレッジの共同体デザイン、地域通貨、共同体教育、パーマカルチャー(持続可能な農的文化)などの事例研究から、カルチュアルクリエイティブス(文化創造者)、先住民から学ぶディープエコロジーの思想まで、未来のデザインのための智恵を伝え、それぞれの地域や現場に生かす仕事をしている。
HP:
http://www.kanatamusic.com/tetra/
YouTube:
https://www.youtube.com/c/テトラノオト

2005年ソフトバンクテレコム 執行役員人事本部長として、ソフトバンクの通信3社の人事制度統合を進めるなど、事業会社の人事責任者として多くの改革を推進した後、2008年三菱商事グループのビジネスコンサルタント会社、シグマクシスの立ち上げにパートナー兼人事ダイレクターとして参画。人事コンサルチームの統括し、数多くの企業を人事プロジェクトで支援する。
その後、2015年にクックパッド株式会社執行役(人事担当)として、再度事業会社の経営に参画し、以降2017年株式会社オウチーノ取締役、2018年株式会社くふうカンパニー取締役とIT関連企業の経営に関わる一方、2016年に自身の人事コンサルティング会社「HCMラボ」を設立し、現在は、くふうカンパニー顧問など、多くの企業のアドバイザーとして人事領域を支援している。
林展宏(以下、林):場所と時間を選ばない働き方こそが、働き方変革の究極の姿だと思うんですね。自分が最大限にパフォーマンスを出せる最適な場所を選択し、柔軟に働ける姿がやっぱり理想なんですよね。リモートワークに関しても、例えば沖縄にいて、東京の会社の仕事をする、海外からの仕事をするというところまでいけば、さらにいい。ですが、日本の企業でどこまでその働き方の変革に踏み込むのかは、経営者の考えに左右されてしまうと思います。
新しいビジネスモデルを作る部署や新しいサービスを開発する部署で働く社員は、常にいろいろなアイディアや発想に思い巡らせながら、トライアンドエラーを繰り返している。外部の知見や情報を取り入れながら、物事を生み出していく作業を行うわけです。そういう人たちを固定的なオフィスに毎日来させて、一定時間を拘束する働き方は、もうあり得ないですよね。日本の企業は、先進国の中でも非常に生産性が低いと言われていますが、私は働き方変革は、生産性向上やイノベーション創出のための、重要なテコになると思っているんです。そこにどこまで踏み込んでいくのかで、企業の今後の成長に差が出てくるような気がしているんですよね。

林:はい、まさしくオフィスの役割や機能をどう考えるか。再設計しなくてはいけないと思います。その時に、テレワークの課題をオフィスで解決していくという視点がいいなと思ったんです。雑談の中からアイディアを生み出すようなコミュニケーションは、テレワークではなかなか難しいので、そういう余白のような部分をカバーする空間がオフィスの役割になっていくのかもしれません。
谷崎テトラ(以下、谷崎):もちろん職種によって変わるとは思うのですが、基本的には自宅で仕事ができるような状態、一番リラックスして自分の時間をうまく使えるような状況を作っていくのがいいんだろうと思います。その上で、オフィスは、行くのが楽しみな場所になってほしい。簡単に言えば、プールがあればいいと思うんです(笑)。
プールがあって、フィットネスがあって、なんなら託児所があって、つまりコミュニティとしてのハブになるスペースこそがオフィスという考え方。プールでひと泳ぎした後にカフェで軽くミーティングすると、すごい発想が生まれたりすることはあり得るわけです。つまり、みんなの共有部分、コモンズと呼ばれる空間の設計はすごく重要だと思うんです。

谷崎:はい、まさしく。緊急事態宣言が明けた後に、沖縄の久高島に行って仕事をしていたんです。人口150人ほどの小さな島なんですが、土地の所有の概念が今でもない島なんです。すべて神様からお借りしているだけ。豊かな土地、枯れた土地の不公平がないようにかなり細かく区分けしていて、島民が等しく借りられるというコモンズ。漁の上手い下手で差が出ないように、平等に分配される知恵があったりもするんですね。
それからこの島で面白いのは、中心的な物事はすべて女性が決める、女系の島なんです。島の中心で、一番偉いのは、長老であるおばあちゃん。都会では年寄りの女性は居場所がないようなケースが本当にたくさんあるわけですが、久高島では、とても大切にされている。でも、昔は日本中どこもそうだったんですよね。どうも日本がもともと持っていたコモンズの知恵は、今こそ重要なんじゃないかと感じたんですよね。
そして、海に入るのが何よりよかった。フィジカルな部分で、健康でウェルビーイングを高めていくことは、それぞれの企業ができることなんですよね。
林:そのお話は、私のイメージのさらに一歩先を行くオフィスで、非常に勉強になりました。オフィスの役割と同じように、企業と社員の関係性も変わっていくべきですよね。社員の副業を認めるだけでなく、むしろ推奨していくという動きもかなり出てきているように思います。優秀な社員は、自分の持っているスキルや能力を使って、求められれば他の会社とも関わることになっていく。すると企業は、社員を自分の会社で抱え込むという関係性ではなくなっていきますよね。
旧来の抱え込みの価値観では、優秀な人材はもう集まらない。雇用する側、雇用される側という従属関係から、互いに過度に寄りかからない、依存し合わない、ある種の緊張関係を持ちながらウィンウィンでいられるような関係性に変わっていくべきだと思うんです。むしろ優秀な人材を輩出していく会社になっていくんだという意識転換をしなければ、いい人材は入ってこないんじゃないでしょうか。
谷崎:最後にまとめとして一言付け加えさせていただければ、ポストコロナ社会では、コモンズの概念はますます重要になっていくと思います。もともと所有の概念が生まれたのが、日本においては730年代に天然痘が流行して、墾田永年私財法という形で土地の所有が認められたからなんです。当時の農地に当たるのが、現在では、それぞれの仕事の仕方っていうことだと私は思っているんです。会社に紐付いて小作人のように働くのではなく、自分のタレントを生かすように仕事をするべきだと。ヨーロッパにおいてもペストの流行後に農奴が解放された流れがあったように、新型コロナウィルスによって所有に関しての概念は変わってきていますよね。このシンクロニシティは、未来を創造するための、一つの指標になるのではないかと思っています。