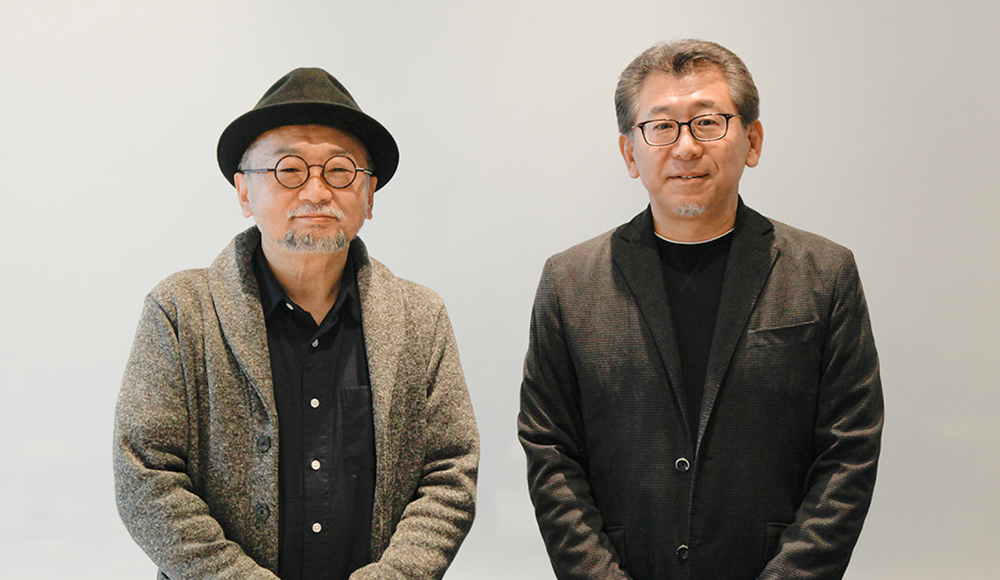
コロナ禍で社会変革の加速化が指摘される昨今。仕事の方法から雇用形態、評価指針やチームビルディングなど、これからのトレンドとして予測される"さまざまな変化"について、谷崎テトラさん、林展宏さんを迎え座談会を実施し、お話を伺いました。その様子を全3回の連載でお届けします。

1964年、静岡生まれ。環境・平和・アートをテーマにしたメディアの企画構成・プロデュースを行う。価値観の転換(パラダイムシフト)や、持続可能社会の実現(ワールドシフト)の発信者&アーティストとして活動は多岐に渡る。アースデイ東京などの環境保護アクションの立ち上げや、国連 地球サミット(RIO+20)など国際会議のNGO参加、SDGs、ピースデー(国際平和デー)などへの社会提言・メディア発信に関わるなど、持続可能な社会システムに関して深い知見と実践の経験を持つ。世界のエココミュニティを取材し、エコビレッジの共同体デザイン、地域通貨、共同体教育、パーマカルチャー(持続可能な農的文化)などの事例研究から、カルチュアルクリエイティブス(文化創造者)、先住民から学ぶディープエコロジーの思想まで、未来のデザインのための智恵を伝え、それぞれの地域や現場に生かす仕事をしている。
HP:
http://www.kanatamusic.com/tetra/
YouTube:
https://www.youtube.com/c/テトラノオト

2005年ソフトバンクテレコム 執行役員人事本部長として、ソフトバンクの通信3社の人事制度統合を進めるなど、事業会社の人事責任者として多くの改革を推進した後、2008年三菱商事グループのビジネスコンサルタント会社、シグマクシスの立ち上げにパートナー兼人事ダイレクターとして参画。人事コンサルチームの統括し、数多くの企業を人事プロジェクトで支援する。
その後、2015年にクックパッド株式会社執行役(人事担当)として、再度事業会社の経営に参画し、以降2017年株式会社オウチーノ取締役、2018年株式会社くふうカンパニー取締役とIT関連企業の経営に関わる一方、2016年に自身の人事コンサルティング会社「HCMラボ」を設立し、現在は、くふうカンパニー顧問など、多くの企業のアドバイザーとして人事領域を支援している。
谷崎テトラ(以下、谷崎):メディアでも大きく取り上げられることが多くなり、SDGsに関心を寄せられている方も多いと思います。私は今年2021年をカーボンニュートラル元年、すなわちCO2排出量ゼロ社会への具体的な行動が始まる最初の年になるのではないかと考えています。トランプ政権からバイデン政権へと代わって、アメリカがパリ協定に復帰することになりました。これでようやく世界中が環境というテーマにおいて、スタートポイントに立ったわけです。単なる理念ではなく、バイデン大統領が220兆円という投資規模を提示して、それに呼応する形で日本でも100兆円規模のグリーン成長が掲げられています。いわゆるグリーン経済成長を展開していく大きな流れがすでに動き始めている。これまでは環境とビジネスは、相反する概念として受け止められていましたが、これからは環境とビジネスが完全に一体化していきます。今まではCSRが進んでいる企業が素晴らしいと言われていましたが、むしろ推進していない企業は市場から退場を迫られるようになっていくはずです。
4月22日23日には、バイデン大統領の呼びかけによって、世界40カ国の首脳が集まって「気候サミット」を開かれましたが、実はアメリカの市民団体「アースデイ」の提言がきっかけなんですね。草の根運動をアメリカの錚々たる企業がサポートし、ついにはトップダウンによって行われるに至る。日本でも意識の高い企業は、この「アースデイ」に呼応する形で動き始めています。

林展宏(以下、林):そうですね。企業が利益だけを追求するよりも、社会貢献や環境に対して貢献していることは、社員のモチベーションにもつながりますよね。身近な例としては、社員同士がお互いに評価し合うサンクスカードというものがあります。本来、感謝される機会の多い社員を高く評価するといった人事考課に使われるケースが多かったものですが、この仕組みを社会貢献のために使っている企業があります。具体的には、社員がそれぞれ集めたサンクスカードの総数をポイントとして蓄積し、半期や年間などの単位でお金に変えて、社会貢献活動に寄付するというものです。この仕組みによって、会社での「感謝される行動」が社会貢献になる、といった新たなモチベーションを生み出すことができます。
谷崎:はい。人本主義、いわゆるタレンティズムという考え方につながっていくように思います。「世界経済フォーラム」の今年のテーマが「グレート・リセット」なんですね。つまり、資本主義のリセット。そこで提示されているキーワードが、タレンティズムなんです。お金中心のネットワークから、人を資本と捉える考え方への移行を示している。これはアメリカの社会学者リチャード・フロリダが10年ほど前から語っていましたが、実は日本においては1980年代に経営学者の伊丹敬之さんが人本主義という言葉を使っていました。従業員主権と分散型シェアリング、組織的市場という現代を表すようなキーワードがすでに語られていたんです。ただし、当時は意識もされず、実装もできなかった。
ところが、2000年代前半になって、リチャード・フロリダがクリエイティブ・シティ、クリエイティブ・クラスという非常に似た概念を語っていく。このクリエイティブ・クラスという考え方は、3つのTで表されるんですが、僕は非常に重要なキーワードだと思っています。その一つが、タレント、タレンティズムという言葉なんです。それからテクノロジー。そしてトレランス、つまり寛容性ですね。この3つが社会と完全に一致したのが、新型コロナウィルスのパンデミックの起った2020年でした。
売り上げではなく、リモートな環境下でいかにタレントを生かしていくのか。そのためにはテクノロジーが必要で、同時にジェンダーを含めた寛容性、つまり多様性をどう組み込んでいくのか。フロリダが言っていたことが全部、形になったんです。

林:今の話を聞いて想起したのは、早稲田大学の入山章栄教授の言葉です。かつて経営はヒト・モノ・カネと言われていたのに、今の世界の流れは、ヒト・ヒト・ヒトだと。要するに人がイノベーションの源泉であり、人が持っている知と知の融合によって、イノベーションを起こしていくということ。
多様性というキーワードが出ましたけれども、ポストコロナになったとしても、働き方はさらに多様になっていくべきだと私は思います。ところが、日本の企業は、どうしてもテレワークを週に2回、出社率は50%といったように一律の基準にはめたがる。なぜなら、管理しやすいからなんですね。ところがテレワークに関して言えば、職種や部門によって適しているものもあれば、そうでないものもある。生産性が上がる人もいれば、そうでない人もいる。要は、多様なシチュエーションに応じた働き方を容認することが重要だと思うんです。ですから、企業は社員の主体性やプロ意識を尊重しながら、働き方を管理するのではなく、仕事の成果を管理するように意識変革していくべきなんですよね。
評価に関しても、実はテレワークだろうがオフィスワークだろうが人事評価の本質はやっぱり仕事の成果であって、組織にどれだけの貢献をしたかで測られるべき。テレワークだから仕事の成果が測りづらいと言うのであれば、人事評価の仕組みそのものが成果を測る仕組みになっていない可能性がありますよね。
谷崎:「場」についての価値観が激変しましたよね。渋谷の再開発のように、情報が集積することによってイノベーションが起きていくという考え方が潮流でした。掛け算が起きるような仕組みを作ることによって、価値を生み出していくという考え方。ところが昨年から、集結することがデメリットとなる時代に突然なってしまった。本来は、様々なタレントを集積させなければいけないのに、集積できない。クリエイティブ・シティ、つまり都市を造ろうと延々考えていたわけですけれども、そうではなく、リモートワークによって成立する環境が必要となったわけです。20年かかるべきことが突然、昨年1年間で起きてしまった。そのコミュニケーションを洗練させ、バーチャル空間において人が集うことができるシステムがあっという間に開発されていった。そこに大きな可能性を感じているから、株価も下がらないんですよね。
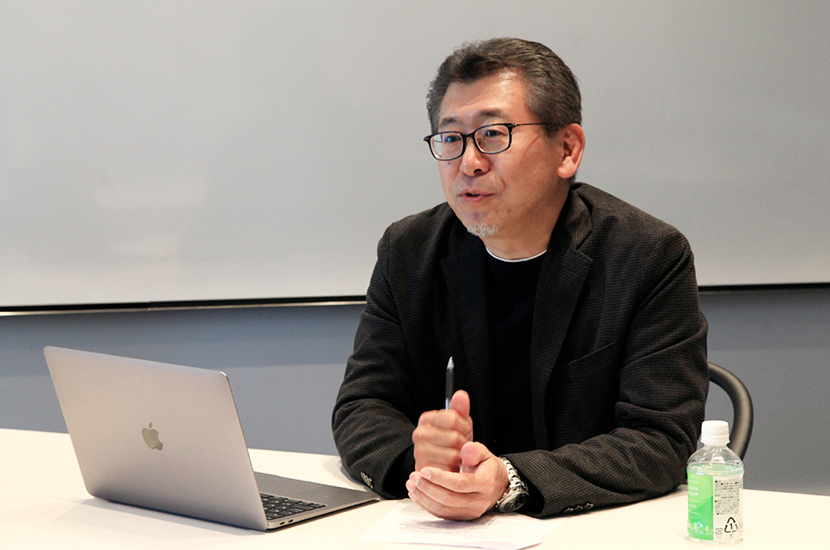
林:私は、会社にいなくてもあたかも会社にいるときのように仕事をすることをテレワークと呼んでいます。つまりは、単に社内での働き方がそのまま自宅などの別の場所に移っただけ。そこにICTが関与する、ということですね。一方でリモートワークは、もう少し自由が高いものと定義しています。会社ではない場所だからこそできる自由な働き方。たとえば自然の中にデスクを持ち出し、集中とリラックスを繰り返しながら自分のペースで働き、結果的には完成度の高い仕事になる。そういった働き方そのものを変化させるのが、リモートワークという考え方です。なので、リモートワークの進展こそが、オープンイノベーションを加速すると思っているんです。谷崎さんがおっしゃるように、10年かかる変化が、去年1年間で起ったという意見は、まさにその通りだと思うんです。コロナ禍で我々は、いろんな気づきを得ましたよね。大きな収穫は2つあります。一つは、毎日、会社に来なくても仕事をして、成果が出せるということ。もう一つはテクノロジーを使って外部の人とつながることがものすごく容易にできると気づいたこと。オンライン会議を使えば、遠方の人でも複数であっても、コミュニケーションの場を設定するのはそれほど難しくないと知ったんです。
個人でも企業でも、やっぱり外部の知見を取り入れないとイノベーションは起きません。その外部の人とつながるハードルが劇的に下がってきているので、雇用形態も多様化していくはずです。社外の専門家と、例えばアドバイザリー契約を結んで手伝ってもらう。あるいは遠隔にいる優秀なエンジニアとプロジェクト単位で契約する。ベンチャー企業ではすでにそういう動きが始まっていますよね。
谷崎:イノベーション・シティと言われたベルリンを調査していると、まずアーティストがある種のアジールのように、空き家を利用するところから始まるんです。クリエイティブなものが始まると、そこにイノベーションのヒントを求めて企業が集まってくる。ただし、アーティストのコミュニティに入るためにはネクタイを外す必要があるんです。つまりフラットな関係が重要視される。雇用、被雇用という関係ではなく、あくまで出会いが大切だと。イノベーションは、そのフラットな関係性の中で起こるものだと思うんです。このコロナ禍においては、物理的な場ではなく、例えばクラブハウスのようなバーチャル空間の中に、その関係性を生み出すコミュニティが作られつつありますよね。