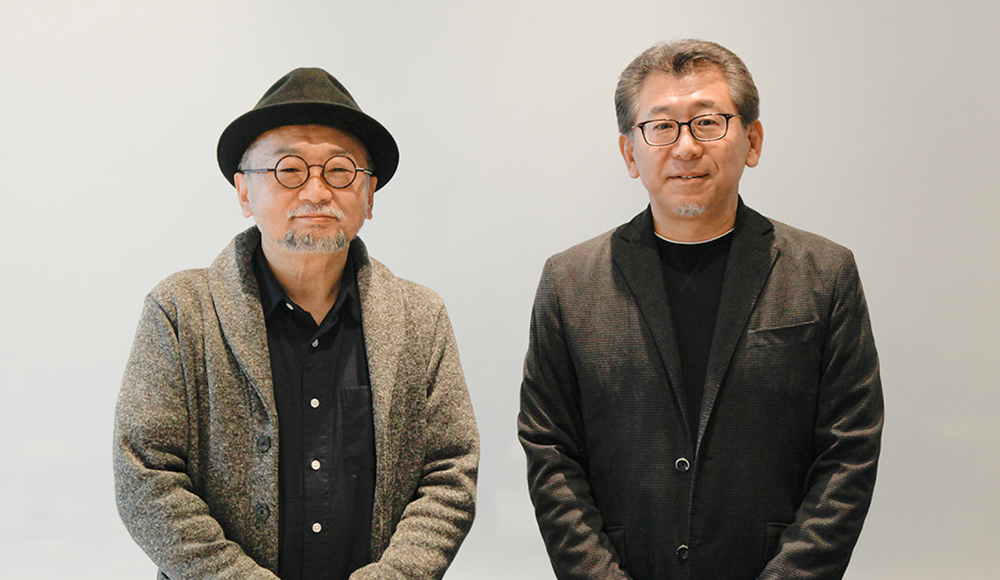
コロナ禍で社会変革の加速化が指摘される昨今。仕事の方法から雇用形態、評価指針やチームビルディングなど、これからのトレンドとして予測される"さまざまな変化"について、谷崎テトラさん、林展宏さんを迎え座談会を実施し、お話を伺いました。その様子を全3回の連載でお届けします。

1964年、静岡生まれ。環境・平和・アートをテーマにしたメディアの企画構成・プロデュースを行う。価値観の転換(パラダイムシフト)や、持続可能社会の実現(ワールドシフト)の発信者&アーティストとして活動は多岐に渡る。アースデイ東京などの環境保護アクションの立ち上げや、国連 地球サミット(RIO+20)など国際会議のNGO参加、SDGs、ピースデー(国際平和デー)などへの社会提言・メディア発信に関わるなど、持続可能な社会システムに関して深い知見と実践の経験を持つ。世界のエココミュニティを取材し、エコビレッジの共同体デザイン、地域通貨、共同体教育、パーマカルチャー(持続可能な農的文化)などの事例研究から、カルチュアルクリエイティブス(文化創造者)、先住民から学ぶディープエコロジーの思想まで、未来のデザインのための智恵を伝え、それぞれの地域や現場に生かす仕事をしている。
HP:
http://www.kanatamusic.com/tetra/
YouTube:
https://www.youtube.com/c/テトラノオト

2005年ソフトバンクテレコム 執行役員人事本部長として、ソフトバンクの通信3社の人事制度統合を進めるなど、事業会社の人事責任者として多くの改革を推進した後、2008年三菱商事グループのビジネスコンサルタント会社、シグマクシスの立ち上げにパートナー兼人事ダイレクターとして参画。人事コンサルチームの統括し、数多くの企業を人事プロジェクトで支援する。
その後、2015年にクックパッド株式会社執行役(人事担当)として、再度事業会社の経営に参画し、以降2017年株式会社オウチーノ取締役、2018年株式会社くふうカンパニー取締役とIT関連企業の経営に関わる一方、2016年に自身の人事コンサルティング会社「HCMラボ」を設立し、現在は、くふうカンパニー顧問など、多くの企業のアドバイザーとして人事領域を支援している。

林展宏(以下、林):働き方変革を進める企業では、上司と部下の関係性も変わってくると思うんです。今までは上司は目の前に部下がいて、その部下を含めたメンバーとの会話のほか、表情や行動を日常的に見ながら、コンディションをある程度、把握できました。ところがテレワークが主体となった環境下では、それがなかなか難しい。すると上司のコミュニケーションに対する考え方も意識的に変えていく必要がありますよね。
例えば1on1のミーティングを定期的に行ったり、チームミーティングを積極的に行ったり。内容に関しても、単純に仕事の進捗やアドバイスをするだけでなく、体調やメンタリティまで踏み込む必要があるかもしれない。コロナ禍でテレワークが自宅でしかできない状況は、いわば歪な形のテレワークになっていると思うのですが、コミュニケーションが不足することで孤独を感じたり、仕事とプライベートの境界がなくなって、つい長時間労働をしてしまったり。そこまでケアするような一歩踏み込んだコミュニケーションが必要なのかなと思っています。
その上で、基本的には仕事の成果と、その成果がどれだけ組織に貢献しているのかで、評価はすべきだと考えています。ただし、プロセスや行動そのものを評価軸に入れる企業もありますよね。すると上司はそのプロセスまでは見られない可能性もある。それをカバーするためには、一緒に仕事をしているメンバーからのフィードバックを評価の参考にするのは、ある程度、有効ではないかと考えています。評価の客観性や納得性を高めるためには、制度をどれほどよくしても実はあまり変わらない。必要なのは、上司がたった一人で評価を決めないということだと思っているんです。できるだけ複数の目で見て、その人がどうだったのか。上司の気づかない面を複眼的に判断していくのが、唯一の方法だと思っています。

谷崎テトラ(以下、谷崎):昭和の高度成長期のように、現在も「生産性を高めるために、人を機械のように扱う」というマインドセットの企業は、苦境に立たされていると思います。古い価値観のまま、叱咤するようなリーダーシップこそがあるべき姿だと思っていたリーダーが、実は一番苦しんでいますよね。生身の人間としての心や体だけでなく、その後ろに家族がいるとしたら、その家族まできちんと企業がケアするという視点が必要で、きちんとできている企業が、伸びているんだと思います。
よくジェンダー問題と言いますが、ジェンダー問題が女性の問題だと思っている会社はダメなんですよ。つまりジェンダー問題は、メンズクライシスなんです。それこそがリーダーシップだと思ってパワハラ、セクハラ、モラハラをやり続けてきた人たちは、どうしていいかわからないで苦しんでいるわけです。
スウェーデンでは、メンズクライシスセンターを全国におよそ30カ所設置しています。男性性によって支配的コントロールで命令し、機械のように効率的に働かせるという思考は成立しない時代にもかかわらず、それ以外の方法がわからない。そのリーダーたちの心と体をケアしながら、思考を更新していくことが、今すごく大きなポイントになっていると思いますね。
その視点はコミュニケーションの問題にも通じるかもしれません。僕は今、京都の大学で教えていますが、顧客である学生の満足度を高めるために、教授全員が集まって、まずコミュニケーションのワークショップを行うんです。それぞれの教授は、専門的な知見は持っているけれど、実は伝えることが苦手な人が多いわけです。でも、教授たちのコミュニケーション能力を育てることによって、顧客の満足度も高まり、大学という組織としてのクリエイティビティも上がるという前提に立って、組織改革が進められていますね。

林:そもそもリーダーシップとマネジメントの違いをどれだけ理解しているのか、という問題があります。これはトレーニングを行うと如実に分かりますが、多くの人が明確に区別できていないんです。マネジメントは組織を統率するために必要な能力で、組織目標に向かって計画し、指示や命令を出してメンバーに遂行させる。その動機付け、求心力は、マネジメントが持つ権限や評価で、それらによって人を動かすという側面を持っています。一方でリーダーシップは、メンバーの多様性を理解して、共感して、自分自身を道しるべとして示しながら、メンバーの成長をサポートしていくこと。そうやって全体の成果を上げていくのが、本来のリーダーシップなんです。この観点を強めていかないと人はついてこないし、企業の成長はなかなか難しくなっていますよね。
谷崎:大学の顧客である学生は、いわゆるZ世代なんですね。彼らは入学した時からリモートがデフォルトという世代。彼らは、我々とはまったく違う感覚で生きていますよね。例えば集中力の持続時間がどんどん短くなっていくというレポートがあります。ミレニアム世代までは10秒ほどあったものが、Z世代には8秒にまで短くなっていく。Twitterが現れた時に140字で世界を表現するって、短いなと思ったんですが、例えばTikTokに関しては15秒ですよね。ロングバージョンでも1分間。その短い時間に情報をやり取りしなければ集中もできないというのがZ世代の特徴なんですね。僕はYouTubeで毎日コンテンツを出していますが、学生たちにも7分間で自分の考えを話せるようにしましょうと話しています。なぜ7分間かといえば、8分以上になると動画内にCMが入ってしまうから。レポートもできるだけ短いほうがいいと話しています。なんなら最初の3行でわかるようにしてくれと。そういうコミュニケーションスキルが、これからは必要になってくる。そして、教授たちへの評価も、どういう論文を書いているかではなく、学生に対してどれだけ満足度があるかを重視する流れになってきているので、それに合わせた発言の仕方をしなければいけなくなっていますよね。