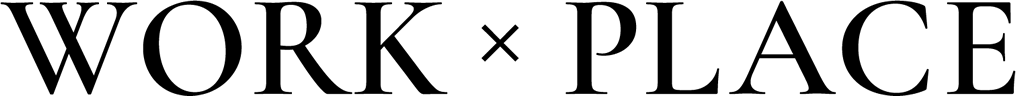
時代とともに変化するオフィス環境。働き方に求められる多様性。
企業価値を高めるために必要な仕組みや、社会課題となっているテーマにフォーカスし、ご紹介します。

ワーカーにとって、ときには給与以上にモチベーションの源泉となる「仕事へのやりがい」。それをどう作るかが、ワーカーにとっても、企業にとっても、大きなテーマとなっています。そこで今、注目されているのが、「ジョブ・クラフティング」という概念。どんな仕事も、自分で創意工夫しながら主体的にやりがいを見出していくという考え方です。すでにこの概念を取り入れているワーカーたちは、どのように仕事をしているのでしょうか。実際の事例をもとに確かめます。
本コラムでは以前、ストレスを無理になくそうとするのではなく、上手に付き合いながら、仕事の効率や個人の幸福感を高めていく「ストレスコーピング」という方法をご紹介しました。「ジョブ・クラフティング」は、ストレスの原因となる仕事の"やらされ感"を取り除き、やりがいを高めていこうというもので、ストレスコーピングにつながる考え方といえます。
ジョブ・クラフティングに似た概念として「ジョブ・デザイン」が挙げられますが、明確な違いがあります。ジョブ・デザインにおいては、会社組織やマネージャーなどが働きがいのある職場や職務を設計するため、ワーカーは与えられる立場にいます。一方のジョブ・クラフティングは、ワーカー自身が主体となって仕事のやりがいを作ります。「クラフト(craft)」には、「手作業で作る」などの意味があります。ワーカー自ら今の仕事を手作りでアレンジし、自主性を高めていく。それにより仕事の効率が上がり、働きがいを示す「エンゲージメント」の向上にもつながります。

どんな仕事も、ジョブ・クラフティングで「楽しい仕事」に変えられる、3つのポイントがあります。1つ目は、仕事の「認知」を変えること。例えば、データ入力を任されたとき、「単純作業でつまらない」と考えるか、「会社の現状が見えておもしろい」と考えるか、捉え方によって気持ちに違いが生まれます。仕事への認知を前向きにできたら、次は「タスク」を変えます。データ入力であれば「効率を高め、短時間でより多く入力する」といった具合に、目標を設定することで、チャレンジする気持ちや成長への実感が生まれます。3つ目は「人間関係」の見直しです。仕事がつまらないと感じている人は、周囲とのコミュニケーションが希薄になっている可能性があります。仲間と休憩時間に趣味の話をしたり、他部署に書類を持っていくときに雑談を交わしたり。少しの工夫で、モチベーションも上がります。
ジョブ・クラフティングの好例とされるディズニーランドの清掃スタッフも、見事にこの3ステップがあてはまります。ディズニーランドの清掃スタッフは単なる「清掃員」ではなく、「ゲストをもてなすキャスト」の一員と位置づけられており(認知の変化)、時にブラシで地面にキャラクターの絵を描くなど、主体的かつ柔軟に来場者を楽しませます(タスクの変化)。来場者ともコミュニケーションを取りながら(人間関係の変化)、仕事を楽しんでいるのです。

会社や上司のサポートがあれば、ワーカーはよりスムーズにジョブ・クラフティングを実践できます。まず、企業がすべきことは、ジョブ・クラフティングについて考える時間を提供することです。就業時間内に業務を詰め込むよりも、自分の仕事を見直す時間をしっかりと確保し、やりがいを持って仕事に取り組んでもらったほうが、結果的には生産効率が上がり、成果も大きくなるのではないでしょうか。
ワーカーがジョブ・クラフティングについて考え、実践し始めたら、上司はワーカーの変革を尊重しましょう。ここでもし批判的な態度を取ってしまうと、ワーカーは再びやりがいを失ってしまいます。規則に違反しているなどの明確な理由がない限りは、仕事のやり方をなるべくワーカーに任せるように意識することが大切。進捗状況の確認など、「報・連・相」の頻度が多くなりすぎると、ワーカーにとっては過干渉と感じられるため、注意が必要です。
オフィスの工夫で、ジョブ・クラフティングをサポートすることも可能です。ワーカー同士の交流を活性化する「フリーアドレス」は良い人間関係に貢献できる取り組みですが、せっかく導入しても、結局は席が固定化されてしまい、あまり意味がないと感じている企業も多いのではないでしょうか。そこで、一工夫している企業もあります。例えば、カルビーでは1日2回の席替えを行っています。「ダーツ・システム」と呼ばれる、ランダムに席が決まる仕組みを導入することで、さまざまな部署のワーカー同士が隣合わせで働いているそうです。
「ほぼ日手帳」で知られるほぼ日は、フリーアドレスではなく、固定席を採用していますが、部署ごとで固まるのではなく、多様な職種のワーカーが入り混じる座席配置にしているのだとか。さらに4カ月ごとに席替えを行って、ワーカーをシャッフル。コミュニケーションを活性化させています。

ジョブ・クラフティングはワーカーの自律性を高めますが、行き過ぎると「その人にしかできない仕事」が生まれるおそれもあります。「あの人の仕事は誰も引き継ぎができない」とならないためにも、認知・タスクとともに、人間関係は非常に重要な要素。ワーカー同士がコミュニケーションを深められるオフィス改革が、円滑なジョブ・クラフティングにもつながるでしょう。

ジョブ・クラフティングにおいて大切な人間関係。職場内や外部パートナー、お客さまなど、さまざまな関係者とのコラボレーションがうまくいけば、確かに仕事っておもしろくなりますよね。
当社の新本社「渋谷ソラスタ」には、その名も「COLABO!」というグループ従業員のための交流スペースが設置されています。普段はコワーキングスペースや打ち合わせスペースとして利用可能なため、私もよくここで仕事をします。いつもとは異なる景色を味わえるだけでなく、他部署やグループ会社の面々と顔を合わせることができるので新鮮。いわば毎日席替えをしているようなものです。
実は、このCOLABO!はイベントスペースとしても活用されています。なかでも「ナレッジ・カフェ」や「ナレッジ・フォーラム」という、グループの内外から講師を招いて開かれる勉強会は盛況。日々の業務に追われていると、ついつい視野が狭くなりがちですが、こういう場で新しい視点やアイデアに触れると刺激になります。私自身、いろいろなコラボレーションを意識しながら、ジョブ・クラフティングを実践していきたいと思います。