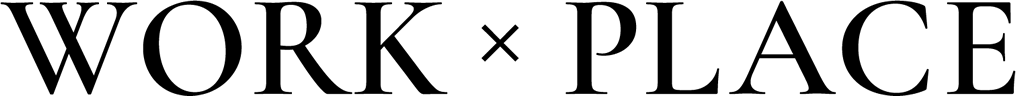
時代とともに変化するオフィス環境。働き方に求められる多様性。
企業価値を高めるために必要な仕組みや、社会課題となっているテーマにフォーカスし、ご紹介します。

仕事が山積みで片付かない。大きな仕事を任されてプレッシャーを感じている。上司からパワハラを受けている。現代ワーカーは多様なストレスを抱えています。こうしたストレスにうまく対処できないと、健康にも悪い影響が出て、仕事どころではありません。そこで昨今注目されているのが、ストレスをゼロにしようとするのではなく、上手に付き合っていく「ストレスコーピング」という方法。導入するためのポイントを解説します。
厚生労働省が発表した2018年の「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、現在の仕事や職業生活に関することで、「強いストレスとなっていると感じる事柄がある」と答えた労働者の割合は58%にのぼりました。ちょっとしたストレスではなく「強いストレス」を感じる人が半分以上というのは、深刻な状況といえます。ストレスを放置していると、個人にとっても会社にとっても大きな不利益が生じます。仕事への意欲が低下し、効率が低下。さらに仕事が溜まっていくという悪循環も発生するでしょう。メンタルヘルスの不調で、ワーカーが会社を長期間休むことにもなりかねません。

こうしたワーカーへのストレス対処方法として、「ストレスコーピング」という手法があります。コーピングには「うまく対処する(cope)」という意味があります。この言葉からもわかるように、ポイントはストレスを完全に消し去るということではなく、うまく付き合っていくということ。ストレスは必ずしも悪いものとは限りません。適度なプレッシャーや不安を乗り越えてこそ、いい仕事が成り立ちます。
ストレスコーピングには、「問題焦点型」と「情動焦点型」の2種類の方法があります。それぞれの特徴を解説しましょう。問題焦点型のストレスコーピングとは、ストレスの原因となっている「ストレッサー(人にストレスを与えている刺激)」を見つけ、それを取り除く方法です。たとえば暑さ、痛み、騒音、病気、怒り、悲しみなどがストレッサーになりえます。職場では、人間関係のトラブルやノルマ、通勤時間などが該当するでしょう。問題焦点型のストレスコーピングでこれらのストレッサーをなくそうとするのであれば、配置転換する、仕事を分担する、出社時間をラッシュの時間からずらす、といった対応が考えられます。ただし、問題焦点型のストレスコーピングでは、周囲の人を巻き込んでしまうリスクもあります。また、ストレスのもとを断ったとしても、また新たなストレスが発生して同じことが繰り返されることもあります。
情動焦点型のストレスコーピングとは、ストレスを感じている人の感情をコントロールしながらストレスに対処する方法です。重要なプレゼンが近づいていて不安が募っているようであれば、気晴らしにスポーツやヨガ、小旅行など別のことをしてみる。ノルマに追われているのであれば、その状況を同僚に聞いてもらい気持ちを軽くする。チーム内に相性の悪い人がいるのであれば、その人のいい面だけを見るようにする。ストレッサーそのものがなくなるわけではありませんが、ストレスとうまく付き合うことで、感じているストレスを減らしていきます。問題焦点型が労働環境を変えることに重きを置いているのに対し、情動焦点型は自分の感情をうまく変えていくことに重きを置いた対応法といえます。
ワーカーが1日の大半を過ごすオフィス環境は、問題焦点型と情動焦点型、両方に影響を及ぼす要素といえそうです。では先進的な企業は、どのようなオフィスづくりを行っているのでしょうか。ストレスコーピング発祥の地、アメリカの事例から見てみましょう。『トイ・ストーリー』や『カーズ』などで知られる映像制作会社のPIXARでは、ワーカーが自分の仕事に集中できるよう、一人ひとりにマイデスクならぬ、マイルームが与えられています。部屋の装飾などは、自分が仕事をしやすいように自由にカスタマイズできます。ストレスの感じにくい環境づくりは、問題焦点型のストレスコーピングといえるのではないでしょうか。さらに敷地内には、オープンカフェやプール、バスケットコート、サッカー場まで完備。ワーカー同士のコミュニケーションや気分転換の場として使われており、情動焦点型のストレスコーピングに役立ちそうです。
ワーカーがジョブ・クラフティングについて考え、実践し始めたら、上司はワーカーの変革を尊重しましょう。ここでもし批判的な態度を取ってしまうと、ワーカーは再びやりがいを失ってしまいます。規則に違反しているなどの明確な理由がない限りは、仕事のやり方をなるべくワーカーに任せるように意識することが大切。進捗状況の確認など、「報・連・相」の頻度が多くなりすぎると、ワーカーにとっては過干渉と感じられるため、注意が必要です。

狭い日本では、さすがにここまで思い切ったことをするのは難しいかもしれません。それでも集中したい人向けにコンセントレーションブースを設置したり、リフレッシュするための空間を設けたり、さまざまな工夫をする企業が増えつつあります。たとえばメットライフ生命のオフィスには、ゲームルームが設置されており、ワーカーは休憩時間に卓球やダーツ、テレビゲームなどを楽しめます。また、LINEのカフェテリアには、あみだクジやけんけんぱ、レゴなどの懐かしい遊びができる仕掛けが施されています。実際に遊ばなくても、そういうものがある空間というのは心が和むでしょう。さらに、窓際の一角には「ごろ寝スペース」も。ここまで来ると、まるで家のようです。
ただし主に予算面の問題から、ストレス削減に向けたオフィスづくりに躊躇する会社も多いのではないでしょうか。そうした場合は、お金をかけない選択肢を検討してもよいかもしれません。
たとえばアロマの香りや観葉植物は、気持ちをリラックスさせ、前向きに働く気分を高めてくれる効果があります。オフィスで使われているイスの座り心地や、デスクの使いやすさ、照明の明るさ、温度や湿度なども、快適な状態を心がけておかないと、体の不調を招いたり、ストレスの原因になったりもします。ワーカーの意見を聞きながら、時々見直すといいかもしれません。また、物理的なものを変えていくだけでなく、仕事に関連するポジティブな心理状態「ワーク・エンゲージメント」を高めていくことも大切です。

冒頭で紹介した厚生労働省の調査によれば、メンタルヘルスケアに取り組んでいる国内企業の割合は59%。強いストレスを抱える人の数を考えると、まだまだ高い数字とはいえません。企業にとってもワーカーの健康管理は大きな経営課題です。効率的に、クリエイティブに、そして長く働いてもらうために、ストレスコーピングを取り入れてみてはどうでしょうか。

ストレスコーピングという言葉をご存知なくても、皆さんそれぞれに気分転換やリラックスの方法をお持ちではないでしょうか。私が最近ハマっているのが観葉植物のお世話。葉がぷにぷにしている多肉植物やずんぐりむっくりしたコウデックスなど、数種類のグリーンたちと生活を共にしています。葉が生い茂ってきたり、幹が太くなってきたり。力強く生きている姿になんだかほっこりさせられています。
実際、植物が人に良い影響を及ぼすことは、さまざまな研究によって証明されています。東急不動産のオフィスビルでは、この緑の力を取り入れた「Green Work Style」を展開中。当社の新本社「渋谷ソラスタ」でも、約250種類の植物を配置し、その効果を検証しています。
オフィスでも自宅でも、予算をかけず、簡単に取り入れられるのが観葉植物の魅力。おすすめですよ。