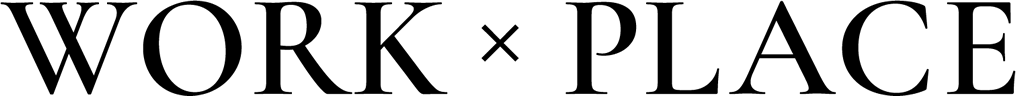
時代とともに変化するオフィス環境。働き方に求められる多様性。
企業価値を高めるために必要な仕組みや、社会課題となっているテーマにフォーカスし、ご紹介します。

ミレニアル世代やZ世代以降の若者たちは、ゆったりした空間で仲間とのんびり過ごす「チル」な雰囲気を好むそうです。「一旗揚げる」といった野心や欲が少ない安定志向で、ワーク・ライフ・バランスを重視する──そんな若者たちの、仕事へのモチベーションや成長意欲を引き出すために、企業は何ができるでしょうか。彼らが「チル」を好む背景を知ることで、若手社員のビジネスへの貢献を促す効果的な方法を探ります。
2019年11月に発表された「楽天ヒット番付2019」で、西の小結に「チル消費」が選ばれました。「チル消費」とはキャンプやグランピング、自宅でくつろぐ時間などに使われるアイテム関連の消費を指します。そもそも「チル」は英語の「chill out(チルアウト)」が由来の言葉で、「くつろいだ」「落ち着いた」「まったりした」など、場の雰囲気やそこにいる人の心持ちを形容する俗語です。「チルってる」「チルい」「チルみがある」などのように使われ、自宅やカフェ、旅行先などで、何をするでもなく一人で、あるいは気のおけない仲間とゆったり時間を過ごす、そんなイメージを表現しています。
本来、「chill」には「ひんやりする」「冷たい」という意味があり、それが転じて米国ではかなり昔から、ゆったりくつろいだ状態のことを「chill out」「chilling」などと表現していました。1990年代以降、音楽の世界でも「チルアウト系」というジャンルが確立しましたが、スローテンポで落ち着いた曲調ながらも、決して「冷ややか」ではない明るい雰囲気を持つのが特徴です。

ある広告会社の分析によると、ミレニアル世代(Millennials)、その後の世代であるZ世代(Generation Z)の若者たちが「チル化」しているといいます。ミレニアル世代とは米国で生まれた概念で、細かい年代については諸説ありますが、2000年代に成人・社会人となる1989~95年生まれの世代を指し、1980年代から2000年代初頭生まれを指すY世代(Generation Y)ともほぼ重なっています。また、Z世代(Generation Z)はY世代から続く新たな世代で、1990年代後半〜2000年代前半に生まれた若者たちを表す言葉です。
日本におけるこれらの世代の特徴は、長く続いた不況で、「日本の将来は明るい」と信じられない時代に生きてきたことにあります。高額の買い物などはせず、無駄遣いを控える、消費意欲が低いといわれている世代です。また、「スマホネイティブ」でもあり、携帯電話を持つ年頃にはスマートフォンが普及、SNSの利用も当たり前の世代です。常に友人たちと連絡を取り合い、限られた範囲の友人と密な関係を築き、仲間を大切にするのが特徴だとされ、Z世代はその傾向がさらに色濃くなっています。

若者たちの特徴としてもう1つ挙げられるのは、「上昇志向が弱い」ということです。不景気ながらもそれなりに豊かな経済環境のなかで育った彼らは、多くを望まなければある程度満足できてしまいます。右肩上がりの急激な経済成長が望めない今、がむしゃらに働いて稼ぐのではなく仕事もそこそこに、ワーク・ライフ・バランスを取るほうがいい、そんな感覚を持っているのです。
そんな彼らが社会人になった今、企業にとっては「チル化」した若者たちをどのように扱い、成長させ、ビジネスに貢献させていくかが課題になっています。若手のやる気やポテンシャルを引き出すために、企業はどんなことができるでしょうか。
ポイントは、仲間との調和を大切にする彼らの特徴を力に変える、つまり「チーム戦」をさせることです。「一人ひとりを成果主義で評価するのではありません。チームを組んで皆で成果を上げてください。全体で評価します」というメッセージが伝わると、業績が上がりやすくなります。それには人事評価指標などのソフト面の工夫も有効ですが、ハード面、例えばオフィスやファシリティのあり方を工夫することも、やる気を引き出すのに一役買うでしょう。チームの一体感を醸成し、チーム内のコミュニケーションからアイデアが生まれる空間を用意することがポイントです。
例えばチームメンバーがゆったりした空間に集まって、皆でアイデア出しや方向性決めの打ち合わせをする。そんな場面を想定して、大きめのモニターやホワイトボードを備えた、ソファーや家のリビングルームのようなスペースを用意するのは一手です。ほかにも「1対多」の形式では、プレゼンや発表をするときに、座面の高さが異なるイスを用意して「視線の段差」を設けると全員の参加意識が高まるといいます。こうした工夫が「チル化」した世代のチームワークを引き出すことでしょう。
チーム内でのコミュニケーションを活性化できたら、チーム間・部署間の関係性や、世代的に価値観の大きく異なる上司・部下間のコミュニケーションもよくしたいところでしょう。かつては多くの企業で社内レクリエーションやサークル活動、あるいは喫煙所や飲み会、深夜残業のオフィスで行われた胸襟を開いた会話を通して「仕事では直接の接点がない人」との関係が生まれていました。それが仕事やキャリア形成にフィードバックされるようなケースも少なくなかったのです。ある意味、今の若者がいう「チル」な場があったともいえるかもしれません。しかし最近は、働き方改革で長時間労働がなくなり、社員を飲み会などの名目で拘束することははばかられる時代へと変わってきています。
そんな中、社員同士のコミュニケーション活性化を目的に、社内にバーなどのお酒を飲めるスペースをつくる会社も出てきました。また、バーとまでは行かなくても、社内カフェを設置している会社は多く、社内のミーティングだけでなく来訪者との打ち合わせに活用している事例もあります。例えばマザーズ上場企業・ドリコムの社内カフェにはバリスタが常駐しており、本格的なコーヒーが提供されているそうです。そのほか、バリスタ常駐型の社内カフェ導入支援をする企業も出てきており、大手有名企業が利用しているケースもあります。

仕事の合間に「スイッチをオフ」にできる空間を用意するのも、「チル」を好む若者には効果的でしょう。こうした場の空気が社員同士の関係を近づけ、世代間の溝を埋めていく。そして、そこから新しいアイデアやビジネスが生まれることが期待できるのではないでしょうか。

以前、WORK×PLACEでも「ジェネレーションZ」を取り上げましたが、いつの時代にも若者の柔軟な発想や行動というのは、社会に大きなインパクトを与えるものです。上昇志向が弱くてどうする!と嘆くよりも、若い世代のスタイルをどう自分たちの組織に取り込んで活かすかが重要だと感じます。
「渋谷ソラスタ」にある当社の新本社にも、気軽なコミュニケーションや「チーム戦」がしやすくなる仕掛けが取り入れられています。例えば、グループ会社の従業員も自由に出入りできる10階フロアには、東急ハンズのプロデュースによる「ハンズカフェ」を設置。コーヒーマシーンをはじめ、いろいろなドリンクを無料で提供し、暖かみのある照明のもと、リラックスしながらラフな打ち合わせや会話ができるようになっています。ほかにも、同じフロアには靴を脱いでくつろげる人工芝のスペースもあり、まさに「チル」な場です。
私自身、固定席だった以前のオフィスに比べ、今は多様な「はたらく場」があるので、構想を練ったりアイデアを考えたりするときは窓際の緑が多いエリアに、企画書の作成などパソコンに向かうときは集中ブースに移動、といった行動を自然に取るようになりました。オフィス移転は、新しい世代を受け入れる側にとっても、発想を転換する"いいきっかけ"になりますね。