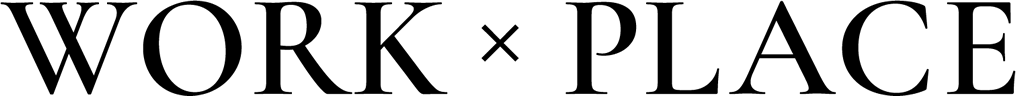
時代とともに変化するオフィス環境。働き方に求められる多様性。
企業価値を高めるために必要な仕組みや、社会課題となっているテーマにフォーカスし、ご紹介します。

多様な人材をミックスし、化学反応を起こしていく。そうした理想とは裏腹に、全社横断プロジェクトやオープンイノベーションなどの新しい取り組みが、空中分解してしまう例は珍しくありません。失敗の理由は、従来型のチーム運営の手法を引きずっていることにあるのかも。そこで今回は、どんな条件でも高いパフォーマンスを発揮できる、チームワークの進化系「チーミング(teaming)」をご紹介。柔軟性の高い組織づくりに貢献するオフィス環境についても取り上げます。
「チーム」には、個人では成し得ないことを達成できる力があります。より大きな目標を達成するには、スポーツチームに代表されるように、固定化されたメンバーが各々の役割に応じてスキルを磨き、結束力を高めていくことが、従来の王道とされてきました。しかし、イノベーションが求められる現代のビジネス現場では、新たなアイデアを生むため、全社横断プロジェクトを立ち上げたり、社外とのコラボレーションを促進したり、あの手この手で「脱・固定化」が図られています。また、目まぐるしく変わる市場環境や顧客ニーズに対応するため、短期集中型でプロジェクトを動かす場面も増えています。
とはいえ、全社横断プロジェクトなどの新しい取り組みが途中で頓挫してしまう例は少なくありません。互いによく知らない者同士が集まり、それぞれの役割も明確ではなく、与えられた時間もごくわずか。固定化されたチーム形態とは全く異なる条件なのに、リーダーやメンバーが従来のマインドや行動パターンをひきずっていると、うまくいくはずがないのです。そこで取り入れるべきなのが「チーミング」の発想です。動詞であることからもわかる通り、チーミングは環境や状況に応じて、個々の役割や連携の方法を柔軟に変化させていく、動的な集団活動そのものをさします。チーミングを実践することで、あいまいで不安定な条件下でも高いパフォーマンスを発揮し、自ら道を切り開くことのできる集団となるのです。

では、チーミングを成功させるにはどうすればいいのでしょうか。チーミングでは、仕事のプロセスに従うことよりも、仕事のプロセスを発展させることが重視され、「学習し、実行すること」に価値が置かれます。仕事をしながら、同時により良い手法がないか探求し、次に活かす、といった具合です。リーダーはそうしたチーミングの価値観を自ら実践して示しつつ、集団内に4つの特別な行動を定着させる必要があります。
定着させるべき1つ目の行動は、「率直に意見を言う」ことです。質問したり、助けを求めたり、提案したり。建前や隠し事を排除したコミュニケーションが、メンバー同士の理解を深め、また、仕事のプロセス発展に向けたアイデアにつながります。2つ目は、「協働する」ことです。情報を共有し、活動を調整し、意見や感想を絶えず求め合うことは、チーミングを失敗させないために不可欠な要素といえます。3つ目は、「試みる」ことです。これには、試すというだけでなく、「一度でうまくいくことを期待しない」という意味も含まれます。失敗を受け入れる寛容さがなければ、誰もが現状維持に走ってしまい、発展は見込めません。4つ目は、反省や批評を意味する「省察する」ことです。これに時間をかける必要はなく、今までの行動について考え、反省点を一言二言でも口にすることが、良い手法を探求し、活用していく原動力となります。
チーミングの成功事例として挙げられるのが、チリで2010年に起こった鉱山の盤落事故です。事故発生から69日後に、坑内に閉じ込められた33人の作業員全員が無事に生還したことは、世界中で感動を呼びました。その救出活動においては、分厚い岩盤の下のどこかにいる生存者の探索に始まり、狭い空間にすし詰め状態となった作業員たちの健康管理や衛生管理、カプセルを使った作業員の引き上げまで、困難な壁が幾重にも立ちはだかりました。そのなかで、地質学者や岩盤掘削の専門家、チリの政府・行政機関、アメリカ航空宇宙局(NASA)やアメリカ疾病対策センター(CDC)、ハーバード大学など最先端の研究機関が、各々の得意分野を活かして個別のミッションに取り組みながら、ときには連携して、奇跡の救出劇を実現したのです。

このように、国や組織、専門分野などのさまざまな"境界"を越えることで、チーミングは大きな力を発揮します。企業にあてはめると、部署や社歴、役職の壁、さらには会社の枠を越え、多様な知識・スキル・価値観のメンバーが必要に応じて集まり、チーミングによって連携していくことが、これからの成長の鍵をにぎるといっても過言ではありません。
こうした「境界を越える力」を伸ばす上で参考になりそうなのが、IT企業によるオフィスづくりです。もともとIT業界では、プロジェクトごとにメンバーが集い、短期集中型で取り組む開発スタイルが広く定着しています。そのため、柔軟なチーム編成や横断的なコミュニケーションを促進する仕掛けをオフィスに施している例が多くみられます。
例えば、日本IBMの大阪オフィスでは、会議室やオフィスの壁全体がホワイトボードになっており、自由にアイデアを書き込めます。また、多彩なタイプのコラボレーション・スペースも用意されており、チームや部署の垣根を越えて知見を共有できるようになっています。伊藤忠テクノソリューションズでは、テーブルやホワイトボード、モニター、Webカメラなどがすべて可動式となっており、多様なチーム形態に柔軟に対応できるようにしています。このように、メンバーの発想や考えを、その場ですぐに共有できる環境は、チーミングに必要な4つの特別な行動のうちの「協働する」や「省察する」に役立ちそうです。

立場や背景の異なるメンバーとの交流は、考え方や習慣の違いに直面したり、衝突や摩擦を生んだりすることもあるため、「大変」という先入観を持つ人も多いでしょう。そうした抵抗感をなくすため、まずはオフィスをオープンで柔軟性にあふれる空間につくり変えてみてはいかがでしょうか。オフィスから「境界」を排除し、日常的に多様なメンバーと接点が生まれる環境にすることが、チーミングの土台となるかもしれません。

チーミングのポイントである"越境力"を高めるため、当社の新オフィス「渋谷ソラスタ」でもさまざまな取り組みを行っています。その一つが"内部階段"の設置です。
当社では、旧本社の時代から執務フロアが複数階にまたがっていました。エレベーターは混んでいるし、階段は遠いし。よっぽどの用事がない限り、ほかのフロアにはなかなか足を運ぶことはありませんでした。
渋谷ソラスタに設置している内部階段は、ワーカーの上下の移動を促進するためのもの。執務スペースに直結、かつ、階段周辺にはラウンジスペースもあるため、人の停留スポットとなり、偶然の出会いを生むのにも貢献します。私もダイエットを兼ねて、この階段を活用中。旧本社では遠かった他部署の存在が急に身近になった今日このごろです。