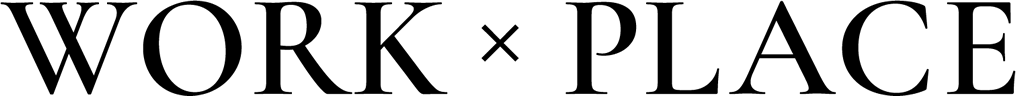
時代とともに変化するオフィス環境。働き方に求められる多様性。
企業価値を高めるために必要な仕組みや、社会課題となっているテーマにフォーカスし、ご紹介します。

「働き方改革」が定着した昨今、各企業では脱・長時間労働の取り組みが進んでいます。しかし、ワーカーのモチベーションはさほど上がらず、社内はなぜかギスギス…。そんな会社もあるのでは。効率化のみを追求する改革では、何かと無理が生じるもの。では、ワーカーのやりがいを高めるには、どうすればいいのでしょうか。悩める企業のヒントになりそうなのが、「パーパス・マネジメント」という個人と組織の意識改革です。ワーカーの幸福感を高め、生産性向上に貢献する、その概念と実践方法をご紹介します。
パーパス(purpose)は本来、「目的」という意味を持ちますが、ここで紹介するパーパス・マネジメントでは「存在意義」と訳されます。「自分たちは何のために存在するのか」「社会や周囲にどのようなメリットを提供できるのか」といった、より根源的な問いを突き詰めるところから、パーパス・マネジメントは始まります。もう一つキーワードとなるのが、ワーカーの「幸福感」です。存在意義を起点に、一人ひとりの幸せを追求することで、働きがいを示す「エンゲージメント」や生産性を向上させる。それがパーパス・マネジメントの考え方です。
パーパスに似た概念として、ミッションやビジョンが挙げられます。ただ、「どうありたいか」というミッションや「どこへ向かうか」というビジョンが未来志向の概念であるのに対し、パーパスは「我々はこうである」という現在地点を明確にするもの。つまり、矢印の始点がパーパスで、矢印の先端がミッションやビジョン、といえます。また、ミッションは「私はこうありたい」という一人称の視点であるのに対し、パーパスは、「社会やコミュニティにこのような影響を与えたい」という、いわば第三者的な視点が加わっている点も特徴です。近年、このパーパス・マネジメントが注目される理由の一つに、ミレニアル世代の存在が挙げられます。現在20代半ばから30代後半で、インターネットに触れながら成長した彼らは、「社会に貢献したい」という意識が強く、パーパスにも高い関心を示すといわれています。

では、パーパスを起点にどうすればワーカーの幸福感を高めていけるのでしょうか。まず前提として、個々のワーカーが企業のパーパスに納得していなければなりません。この企業は何のために社会に存在しているのか。その理由に共感していないと、そこで働く自分の存在意義を見いだせないからです。そこで、企業が自分たちのパーパスについて、わかりやすく丁寧な言葉で表現する必要があります。経営層やマネジメントクラスなど一部の人間に限定せず、ワーカーから広く意見を聞きながら、自社のパーパスについて考えると、共感が広がりやすいようです。
企業のパーパスがまとまったら、ワーカーのパーパスも明確にする必要があります。しかし、自分の存在意義について、すぐに答えられる人は滅多にいません。そのため、企業が研修やコーチングなどを通じて、ワーカーのパーパス探しをサポートすることも大切でしょう。同時に重要なのが、企業が個々の「自分らしさ」を尊重する姿勢を打ち出すこと。個性や価値観を否定する空気は、「自分が生きる目的とはなにか」「どのような価値観を大切にしているか」といった問いから始まる個人のパーパス探しを疎外する要因となるからです。場合によっては、まずは個人のパーパスを明確にした上で、それを持ち寄り、企業のパーパスを考えるという順序でも効果的かもしれません。いずれにせよ、ワーカーと企業、それぞれのパーパスの重なりが大きければ大きいほど、さらには、ワーカーが自分らしく働き、自らの強みを発揮して活躍すればするほど、幸福感は高まるといわれています。
7年連続で増収増益を達成しているネスレ日本では、「生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献します」というパーパスを掲げています。それを「共通価値の創造」という具体策に落とし込み、母乳育児の支援、食品ロスや廃棄の削減、カカオ生産国の支援などの活動を推進しています。同じく業績好調なユニリーバ・ジャパンのパーパスは、「サステナビリティを暮らしの"あたりまえ"に」。その具体的な取り組みとして、パッケージの削減、持続可能な農産物原料の調達、食品・飲料製品の栄養基準の強化などを実施しています。また、同社では社内に向けて「Be Yourself(あなたらしくあれ)」というメッセージを発信。ワーカーに自らのパーパスを見つけるよう促しています。

このようにパーパスが明示されていると、ワーカーも自分たちの存在意義を確認しやすくなり、生産性の向上や個々の幸福度の上昇に結びついていくのです。パーパスの重要性を認識している企業のなかには、ワーカーの幸福を追求する担当役員「CHO(Chief Happiness Officer)」を設置する企業も増えています。
では、ワークプレイスの分野で幸福感に貢献する道はあるのでしょうか。ユニリーバ・ジャパンでは、前述の通り、社内向けに「Be Yourself(あなたらしくあれ)」を掲げており、その一環として、ワーカーが働く場所や時間を自由に選択できる「アクティビティ・ベースド・ワーキング(ABW)」の概念をベースにした、その名も、「WAA(Work from Anywhere and Anytime)」という制度を設けています。自宅や図書館、カフェなど、どこでもいい。ワーカーが自分らしく働き、幸福感を高めてパフォーマンスが向上するよう、サポートしているのです。
このWAAは、全国の自治体や旅館とも提携した取り組みにバージョンアップしています。社員は全国各地の提携施設を無料で利用できますが、その代わりに、地域の特産品の販売促進を支援したり、住民と協力して地域課題を解決したりと、地域社会に貢献することが前提となっています。個人の働き方改革にとどまらず、地域社会のサステナビリティに寄与しているのです。

ワーカーの価値観は、年々多様化しています。ワーカーに自分らしく働いてもらうには、働き方の選択肢を増やしていくことが不可欠ではないでしょうか。まずはパーパスを起点にして、ワーカーの幸福にベクトルを向けていく。そうして個々のパフォーマンスを上げていくことが、今後の企業が生き残る道となるかもしれません。

「Be Yourself(あなたらしくあれ)」。ユニリーバさんのメッセージ、素敵ですよね。「あなたの存在価値とは?」と聞かれると、答えにつまりそうですが、自分の価値観を見つめ、それを大切にするところから始めればいいと考えれば、個人のパーパス探しはそれほどハードルが高くないように感じます。
「渋谷ソラスタ」にある当社の新本社でも、以前ご紹介した通り、「グループABW」を導入し、その日の状況に応じて働く時間や場所が選択できるようになっています。そうした、働き方の柔軟性を高める取り組みだけでなく、一人ひとりの個性や価値観を尊重する「ダイバーシティ&インクルージョン」への対応も推進しています。代表的なのが、性別に関係なく利用できる「オールジェンダートイレ」や宗教・宗派を問わず利用できる「祈祷室」の設置。どちらも共用部である最上階に設けており、当社を含む渋谷ソラスタの全テナントで働くワーカーが、自由に利用できます(画像は最上階にあるスカイテラスの風景)。
「building smiles はたらく人を笑顔に。」というメッセージの下、ワーカー一人ひとりが自分らしく働けるオフィスづくりをめざす当社の姿勢には、心から共感できますし、私もそれに貢献したいと思っています。きっとそれが、「パーパスを重ねていく」ということなのでしょうね。