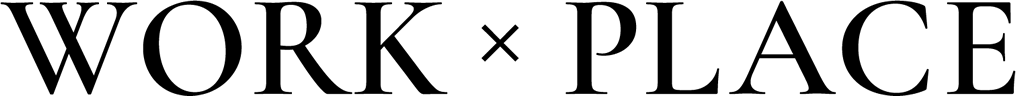
時代とともに変化するオフィス環境。働き方に求められる多様性。
企業価値を高めるために必要な仕組みや、社会課題となっているテーマにフォーカスし、ご紹介します。

「デジタルトランスフォーメーション」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。言われてみれば新聞で見かけた気もする…けれどIT部門ではないのでそれほど気に留めなかった、そんな方も多いかもしれません。デジタルトランスフォーメーションとは何なのか、なぜ今、企業に変革が求められているのか、そして変革遂行のためにはどのようなワークプレイスが必要なのかを、事例も踏まえながら解説していきます。
デジタルトランスフォーメーションは英語で「Digital Transformation」と表記し、「DX」と略します。なぜ略称が「DT」ではないのかというと、英語では「Trans」を「X」と表すことが一般的だからだそうです。このDXという概念は2004年にスウェーデンのウメオ大学でエリック・ストルターマン教授が提唱した「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」というコンセプトが起源といわれています。

似た概念に、「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」というものがあります。アナログだったものをデジタル化する、具体的にはフィルムのカメラをデジタルカメラにするのが「デジタイゼーション」で、デジカメで撮った写真をネットワーク経由で送受信する仕組みにするのが「デジタライゼーション」です。
DXはその流れを組む概念ですが、ずっと影響範囲が広く、これまでの常識だった人の営みや社会が、枠組みごと劇的に変わることを指す言葉です。写真で例えるなら、従来は紙にプリントして一部の人に共有するしかなかったものが、デジタルデータの登場によって皆がSNSを通じて世界中にシェアできるようになった、といったような大きな変化をいいます。
さて、ここまでの話は広義のDXであり、テクノロジー、とりわけインターネットやスマートフォン、IoT、人工知能(AI)やロボティクスなどの発展による、社会全体の変化を説明するものです。では、狭義のDXは何かというと、新しい製品やサービスを生み出す「企業」を主語にしたDXになります。日本では、経済産業省が2018年9月に「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」を公開し、DXという言葉が産業界の注目を集めました。
アメリカでは、Amazonが書籍のEC(電子商取引)を起点に本と読者の新しい関係をつくり、書店・流通・小売業をディスラプト(破壊)してきました。UBERはデジタルの力でまったく新しいビジネスモデルとシェアリングエコノミーを生み、シリコンバレーからタクシー業界を消し去りました。最近では、やはりまったく新しい映像コンテンツの楽しみ方・ユーザー体験を生み出したNetflixの登場で、レンタルビデオ業界は見る影もありません。

このような従来の「業界」や「市場」の枠組みを消し去るほどの変革が、DXなのです。この波は国境を越えてグローバルに広がり、日本企業も生き残りを懸けてDXを成し遂げなければならない状況が迫ってきています。
このDXの推進は、いわゆる「IT部門」だけが担うものではありません。確かにデジタルの力を使うため、ITの専門家は必要でしょう。でも、本筋は新しいサービスやビジネスモデルを生み出すことであり、これまでにないユーザー体験を生み出すこと。従来、IT部門がつくるシステムのユーザーは基本的に社内でしたが、DXにおけるユーザーは社外、一般の消費者です。そのため、さまざまな事業部門の人たちが、DXを「自分ごと」と捉えて推進する必要があります。そして、IT部門と事業部門が一緒になって新しいサービスやビジネスを開発する際のフレームとなるのが、「デザイン思考」です。
デザイン思考を簡単に説明すると、「とにかくユーザーに寄り添い、共感する」「ユーザーの行動を観察し、話を聞き、解決すべき問題を発見して深掘りする」「プロジェクトメンバーで問題解決のためのアイデアをたくさん出した上で、議論の中で整理して、1つのプロダクトやサービスの形に落とし込む」「プロトタイプで試し、検証しながら進化させる」というプロセスを踏む考え方のことです。デザイン思考の実践には、部門や組織といった枠組みを超え、プロジェクトメンバー間でコミュニケーションを密にとる必要があります。そのためには、従来とは異なるクリエイティブな環境の整備が不可欠になってきます。デザイン思考を取り入れる先進的な企業では、社内に専用のデザインスタジオを設けるところもあるほどです。
企業のDX推進に対して、バックオフィス担当者ができることがあるとすれば、この活動を促進するオフィス環境の整備だといえるでしょう。
ヤフーでは、2016年にオフィスを移転した際、フリーアドレスや座席のジグザグな配置、フリースペースの積極配置などを取り入れたそうです。これによってミーティングがしやすくなり、チームワークが育まれて、デザイン思考を進める一助にもなったといいます。また、KDDIでは、社外の人と新しいビジネスを共創し、顧客企業のDXを実現するための場として、「KDDI DIGITAL GATE」を開設しました。そこでも、ビジネス開発のフレームワークとしてデザイン思考が採用されているそうです。

DXを進めるには、部署間、企業間、場合によっては大学や公的機関などとも横に連携し、多様な視点を取り入れることが有効とされています。しかし、これまでの仕事の取り組み方とは大幅に違ってくるため、特に大企業では推進メンバーの意識を変えていくことも必要です。そのためにも、オープンで自由な議論ができる環境づくりは、企業のDX実現の前提といってもよいでしょう。

インターネットやデジタル化の波が押し寄せているということは、日々のニュースで嫌というほど耳にしますが、その意味合いや本質を端的に表すキーワードが、今回の「デジタルトランスフォーメーション(DX)」なのかもしれません。業界や市場の枠組みすら変えてしまうインパクトを持つDX。なんとなく不安になって「追いつかねば」と焦るよりも、「この好機をビジネスに活かそう」と考える企業の方が、結果として世の中をリードしていくような気がします。
私自身は「スマホネイティブ世代」なので、インターネットやスマホがなかった時代の不便さは、なかなか想像しづらいものです。しかし、ここから先、5Gサービスが浸透し、さまざまなデジタル技術が実証実験フェーズから当たり前に利用できる日常へと進化していくと、私たちの仕事やライフスタイルも大きく変化するのかなと、未知の世界にワクワクします。
東急不動産ホールディングスにも、この4月から「DX推進室」が新設されることになりました。さまざまなデータやデジタル技術を活用して、グループ横断的なビジネスモデル革新へとつなげていくための組織です。今回の記事にあるデザイン思考の取り入れをはじめ、新しい働き方、新しいワークプレイスが、ますます重要になってくるのだなと、一担当者としても身が引き締まる思いがします。